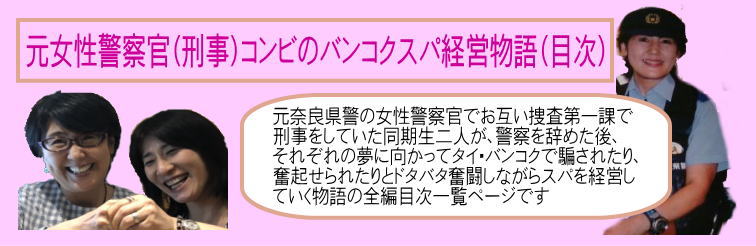今回の登場人物
源九郎とよ(本名土井美苗):復興活動物語のボランティアチームスタッフ代表。この当時は警察官をしておりました。当時は本名を隠してペンネームの「源九郎とよ」で活躍しておりました。
美里:源九郎とよの親友。癌で余命3か月の命。源九郎とよの警察同僚のHくんとは高校の同級生
信貴山朝護孫子寺奥の院の住職のお母さま:無料で様々な相談を受けている有名な霊能者
金峯山修験本宗知足院玄明院岩岸住職:源九郎稲荷神社のお火焚祭を執り行ってくださっている僧侶。以前は信貴山朝護孫子寺奥の院の指南役もされていました。
※ 現在、源九郎稲荷神社は社務所建て直しのためにYoutube、SNS等への登録のお願い等、協力を求めております(ここをクリックしてください)
源九郎稲荷神社のお掃除を始めてから、闘病中の友人美里が退院しました。
美里のことが縁で、今まで縁のなかった神社に触れるようになり神社が大好きになったことと、また夢で見た「三角錐の島の神社」を探すために、巡礼の旅に出ることにしました。
前回は、そんな中、神社に触れる前から縁のあった信貴山朝護孫子寺奥の院に行った際の不思議な霊視のお話しをご紹介させていただきました
前回の記事はこちらから
聖徳太子さんも絡む源九郎稲荷神社との縁
源九郎稲荷神社の復興活動のお話をする中で、復興活動を始めるまでに様々な不思議な神仏との縁を感じる出来事があり、どうしてもその出来事を省くことができないため、今回は、源九郎とよの個人的な話がメインになってしまうことをご了承ください。
源九郎とよは、元々大阪天王寺の生まれです。
近くには四天王寺さんがあり、四天王寺を建立された「聖徳太子」は、私の日々の生活の中で、子供の頃から、ごく自然に存在していた方でした。
毎月22日に開催される聖徳太子さんの縁日は、たくさんの屋台が出て、多くの人が集まることから、まるで夢の国に来たように楽しくて楽しくて、聖徳太子さんというのは、とよにとっては「楽しみを与えてくれるとても良いおじさん」だったのです。
源九郎とよの両親は、信仰とは縁のない人で、家の法要以外は特に神仏と関わることもありませんでした。
なので、当然源九郎とよも信仰とは無縁であり、源九郎稲荷神社に携わるようになるまでは、神仏についてほとんど無知な状態でいました。
ところが祖父は、家柄の良いお坊ちゃん育ちの方であり、俳人で、とても信仰心の篤い方でした。
物静かでいつも微笑んでいて、私は小さい時から、祖父を見ていると仏様を見ているような気がしました。
その祖父は、四天王寺さんを信仰しており、毎朝、四天王寺さんにお参りするのが日課でした。
祖父の家には、赤ちゃんを抱いた弘法大師さんと、聖徳太子さんの像が祀られており、祖母が毎朝お供えをしていました。
とよも、時々「やらせて〰」と言って、お水やお花を換えたりしました。
そのときに唱える、源九郎とよの真言が
「まんまんちゃんあん」
でした。
「毎日ご飯をたべさせてくださってありがとうございます」
という意味の子供語です。
今、祖父の家は既に売却してないのですが、あの2つの像はいったいどこに行ったのか?
ずっと気がかりでいます。
その後
源九郎とよは小学校と、中学校2年まで大阪で暮らし、中学校3年の時に奈良県平群町というところに引っ越して来ました。
悲劇の王である「長屋王」の墓が近くにある、とても静かなところでした。
そして、引っ越しと同時に、「ジュンちゃん」というシェパード犬を飼い、その子を連れて家の裏山に家族で良くハイキングに行きました。
その裏山というのが、信貴山から生駒さんへと繋がる山脈になるのですが、それほど厳しい山々ではないので、子供や子犬の足でも楽しくハイキングができました。
なので、源九郎とよはこの山が大好きになり、一駅離れたところになる中学校の帰り道も、電車に乗らずにわざわざ山の中を歩いて帰ったりしていたのです。
その後、源九郎とよは高校に進学しました。
高校の時は、ソフトボール部の部活に追われていたのと、ジュンちゃんの体が大きくなり連れて歩くのが大変になったため、もう山へのハイキングに行くこともなくなりました。
でも、バイクの免許を取ったことから、休みの日には時々母のバイクを借りて山を散策するようになりました。
バイクに乗るようになってからは、ハイキングでは行けなかった場所にまで足を延ばすことができるようになりました。
そして・・・ある日、ついにこの平群の山脈の中にある「信貴山朝護孫子寺奥の院」に辿り着いたのです。
この時のお寺にたどり着いたときの不思議な感覚は今でも忘れることができません。
お寺は山の中に、ひっそりと建っています。
この日源九郎とよはまるで迷い込む・・という言葉ばぴったりな感じで、このお寺に辿り着いたのです。
辿り着くという感覚では、初めて源九郎稲荷神社を訪れた時と似ています。
ただ、源九郎稲荷神社の時に感じた「なんと寂れた・・寂しい神社なんだ」という印象と違い、この奥の院にたどり着いた時に感じた印象は「神々しい」というものでした、。
お寺には誰もおらず、源九郎とよは声もかけずに入っていいものかどうか躊躇しましたが、とてもお寺の中を覗きたくて仕方がなく、どんどんお寺の奥へと入っていきました。
とても掃除の行き届いた綺麗なお寺でした。
中でも源九郎とよが感動したのは、このお寺の一番奥にある石を組み立てられて作られた石窟でした。
石窟の入口は鉄製の扉があり閉まっていたので、この扉の奥に石窟があるなど普通は気が付かないと思いますが、この時、この扉のがとても気になったのです。
そして、扉に手をかけると鍵もされておらず普通に開いたので、お寺の人に声もかけずに入ってはいけないとは思いながらも、こそっ〰と中に入りました。
少し進むと、石窟がありました。
恐る恐る石窟の中に入ると、そこは日の光が差し込み、キラキラとしていました。
そして中には毘沙門天の石像が祀られていたのです。
本当に綺麗な空間でした。
周りは沢山の木々で囲まれており、その木々の間からも木漏れ日が差し込んでいて、まるで沢山の神様がいらっしゃるような気がしました。
余りの神々しさに、源九郎とよは暫くこの場所から離れることができませんでした。
信貴山奥の院のご本尊は毘沙門天立像で、「汗かき毘沙門天」とよばれています。
このお寺は聖徳太子が排仏派の、物部守屋征伐に出陣した際、毘沙門天が太子軍の先頭に立って汗まみれになりつつ戦い、その活躍により勝利することができたといわれており、聖徳太子さんが歓喜して、この場所にお寺を建立されたそうです。
源九郎とよはこの時初めて「毘沙門天」という仏様の存在を知り、この時から無信仰だったとよが大切に思う仏様となりました。
そして後に毘沙門天さんと聖徳太子さんのつながりを知り、小さい時から縁日で親しんできた聖徳太子さんが「この素敵な場所を私に教えてくれたのかな〰」と思いました。
毘沙門天さんとの出会いは、今でも、聖徳太子さんが結んでくださった縁だと思っています。
聖徳太子様から毘沙門天様へ、そして源九郎稲荷神社へ繋がる神仏の縁
それから奥の院のこの場所は、源九郎とよのお気に入りの場所になり、疲れた時にはにここを訪れるようになりました。
いつ行っても誰もいらっしゃらないので、好き放題にこの石窟に入り、長時間ボーっと過ごすのが、とよの癒しの時間となったのです。
この習慣は、源九郎とよが警察に就職するまで続きました。
でも、警察官になり忙しい日々を過ごし、また数年後には、自宅も平群町から王寺町というところに引っ越ししてしまったため、奥の院を訪れることは全くなくなりました。
ところが、やはりこの奥の院は、源九郎とよとは縁のある場所であったようで、その後、源九郎とよが源九郎稲荷神社の復興活動を行っていく中で力となり協力をしださることとなる「金峯山修験本宗の知足院玄明院 岩岸住職」がこのお寺に大きく関わっている方だとわかったのです。
岩岸住職は、後にとよに信仰の大切さを教えて下さり、源九郎稲荷神社の復興に関して神仏的な部分で多大な協力をしていただきている方です。(お火焚祭を執り行ってださっています)岩岸住職との出会いや共に活動していく話については、この後物語の中で出てきますので、その時にご紹介していきますね。
奥の院に話を戻します。
奥の院はもともと、以前に源九郎とよの霊視をしてくださった女性の旦那様が住職をされていました。
しかし旦那様が病気で亡くなられ、その後を長男さんが継いだそうなのですが、その方もすぐに交通事故で急死されたのです。
それで、お寺から遠ざかっていた次男さんが急遽、お寺を継ぐことになったそうなのですが、お寺を継ぐことなど考えていなかった次男さんは、初めの頃はお経をあげるのもとても不慣れだったそうです。
そこでお母さまが、ずっと懇意にしていた岩岸住職に次男さんの指南役をお願いしたらしく、源九郎とよが岩岸住職に出会ったときには、すでに5年ほど前から信貴山奥の院のお仕事をお手伝いしていたことを知りました。
(現在は、この次男さんも数年前に病気で亡くなられたことから、三男さんがお寺を継がれたため指南役を降りられたそうです)
このことを知った時には、本当にびっくりしました。
四天王寺から信貴山奥の院、そして岩岸住職へと続く縁は、祖父が信仰していた聖徳太子さんから続く縁なのかな?と思っております。
さらに源九郎とよは、この後、聖徳太子が建立された法隆寺がある斑鳩町という土地で働くことになりました。
ここでも、法隆寺に関わりのある藤本さんや中野さんという方と深く縁を結んで行き、お二人も後に源九郎稲荷神社の復興活動をサポートしてくださるようになるのです。(このお話は後に紹介いたします)
とよは聖徳太子から毘沙門天様、そして源九郎さんへと縁を橋渡しされたのでしょうか?
修行をする必要がある未熟なとよを鍛えるために「こいつを鍛えてやってくれ~」と、神仏が橋渡しをしてくださったような気がするのです。
おそらくそういうことは多くの人が経験されているのではないでしょうか?
人と人との縁が必然的なものであるとしたら・・・
おそらく神仏との縁も必然的なもののような気がします。
みなさんが、いろんな方と出会われるのと同じように、神仏とも知らず知らずのうちに縁を結ばれているのかもしれませんよ。
源九郎とよ以外にも、源九郎さんとの縁を結ばれた方はたくさんおられます。
きっとその方の人生の中で、源九郎さんが大切な存在になられた方も多くおられると思います。
そうやって、ひとりの人生、生活、心の中に大切な神様や仏様が存在してるといことは、本当に素晴らしいことだと思います。
今では源九郎さんも、多くの方の心の支えになられているはずです。
あの、誰にも見向きもされたかった源九郎稲荷神社が、今ではたくさんの人が参拝される神社になりました。
今、考えると・・・
参拝くださる方々や神社のお手伝いをしてくださる方々も、源九郎とよのように神様や仏様から源九郎稲荷神社に繋がる縁の橋渡しがあったのではないでしょうか?
ということで・・源九郎とよは毘沙門天という仏様に導かれて、やがて源九郎稲荷神社への復興活動へと進んでいくのです。
番外編の記事はこちら
源九郎稲荷神社復興活動に続く「源九郎とよのバンコクスパ経営奮闘記」
源九郎稲荷神社がある程度復興して、多くの方が参拝に来てくださるようになった2014年、とよはある決意をします。
それまで勤めていた警察を辞めて、タイ、バンコクで新たな挑戦を始めることになったのです。とよが源九郎稲荷神社復興活動チームから離れて、警察同期生だった親友の助けを得ながら異国タイで奮闘するハチャメチャな様子を綴った物語が「元女性警察官(刑事)コンピがバンコクでスパ経営物語」です。
なんとか成功してお金を貯めて源九郎稲荷神社の社務所を建て替えるのがとよの夢なのですが、新型コロナウィルスのパンデミックもあり、なかなかすんなりとはいかない状態です。
でも、夢をあきらめずにやれるところまで頑張ってみたいと思います。ご興味のある方は、そんな源九郎とよの奮闘状況をご覧ください。
元女性警察官(刑事)コンビのバンコクスパ経営物語